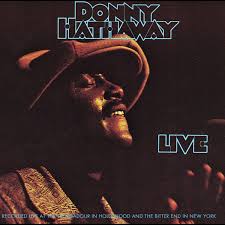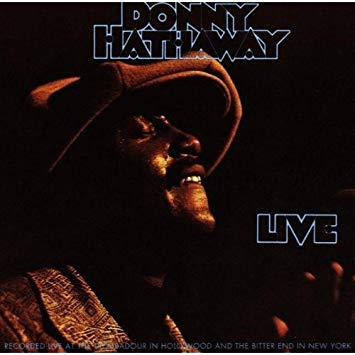鍵盤担当です。
アルアルの会話。
友達:「バンドやってるの?どんなの!?」
ぼく:「洋楽のカバーだよ」
友達:「え?何?誰のカバー?」
ぼく:「いやー、あんま知らないと思うけど(^^;」
友達:「え?どんなのどんなの?」
ぼく:「AORとか、ブラコンのカバー。」
友達:「ふ~ん・・・(^^;」
無理もないです。ニッチといえば、ニッチなジャンルですし、そもそも、最近はあまり一般的に聞かなくなってしまったワードかもしれません。
そこで、このコラムでは、YSPが演奏しているジャンルについて、お話してみたいと思います。
【AORとは】
「AOR」とは、「Adult Oriented Rock」の略で、直訳すれば、「大人のためのロックミュージック」となります。
音楽のジャンル呼称は、時代の流れとサウンドの変遷や、リスナー個々の受け止め方により、変わるものだと思っていますが、ここでは一旦、AORを「1970年代後半から1980年代前半までに流行した、ブラックミュージックから影響を受けた白人ミュージシャンによる音楽」と定義します。
【ブラックミュージックの変遷】
ブラックミュージックのルーツは、20世紀初頭のアメリカ南部に発祥したブルースにあるといっていいでしょう。
ギターによるシンプルなコード展開(3コード)と、ボーカルの内なる感情表現が特長です。
ロックを中心とした白人音楽にも多大な影響を与えています。

やがて、それはジャズに発展します。
コード展開がやや複雑になり(テンションコード)、またドラムやベース、ピアノ、管楽器、オーケストレーションと、使用される楽器の幅が広がり、即興演奏も行われるようになりました。
また、リズムも、ラテン系との結びつきなど、より幅が広がり、黒人音楽の枠組みを超え、音楽性が自由かつ多様になっていきます。

一方、ブラックミュージックの枠組みの中では、ブルースから影響を受け、歌唱表現やリズムがより激しい音楽が台頭し始め、「リズム&ブルース(R&B)」と呼ばれるようになります。

R&Bという表現は、後に、黒人音楽を超えて、今では日本の国内アーティストまでもがカテゴライズされる超広義のワードになりましたが、1960~70年代頃は「ソウルミュージック」と呼ばれていました。
今でも、数少ないレコードショップでも、洋楽のコーナーには「ソウル/R&B」というコーナーがあり、両者を明確に区別することは難しいです。
また、1960年代以降は、ヒットチャートとの結びつきが強くなり、ビルボード等のヒットチャートを賑わしました。
ここで重要なのが、歌唱ももちろんですが、ベースを中心としたウネるようなリズム(グルーブ感)です。
【白人音楽の変遷】
同じく1950年代頃から、白人層において、ブルースから影響を受けたロックンロール、やがて、ロックが台頭していきます。
特にロックは、1960年代頃から、ギターを中心とした8ビート主体の更に激しい音楽性で特に若年層から人気を得て、前述のソウルミュージックと並び、ヒットチャートを賑わし、以降、メジャーなジャンルとして発展していきます。
一方、1970年代後半頃から、ロックから激しさを取り除き、ソフト/メロウな曲調や、ジャズの持つ洗練されたコードワーク、ブラックミュージックの持つグルーブ感も取り入れ、より都会的なイメージを持つ音楽が、徐々に姿を現します。それが、「AOR」です。
一般的に、Boz Scaggsがアルバム「Silk Degrees」をリリースした1976年がAOR元年と言われています。
このアルバムは、後に、TOTOを結成するメンバーがレコーディングに携わったことでも有名です。
AORを語る上で、こうした卓越した演奏技術を持つスタジオミュージシャン達のプレイは不可欠ですし、ライナーノーツ(最近は、死語になりつつありますが(^^;)のクレジットで、楽曲の提供者や、プレーヤーを確認しながら聴くことも、AORを聴いていく醍醐味です。
ロックのように、カッチリとしたバンド形態でない場合も多く、かといってR&B/ソウルのように、シンガーのキャラがひと際目立つようなことも、やや少ないのが特長ともいえます。
もちろん、AORの中でも、比較的シンプルな演奏の楽曲もあれば、非常に難解なことをさらりと演奏している場合もあり、様々ですが、総じて聴きやすい音楽ジャンルだとは思います。
YSPのレパから数曲・・
さて、ここまでまとめると、下の図のような感じでしょうか。。。
(小学生の時に習った懐かしの「ベン図」を描いてみました)
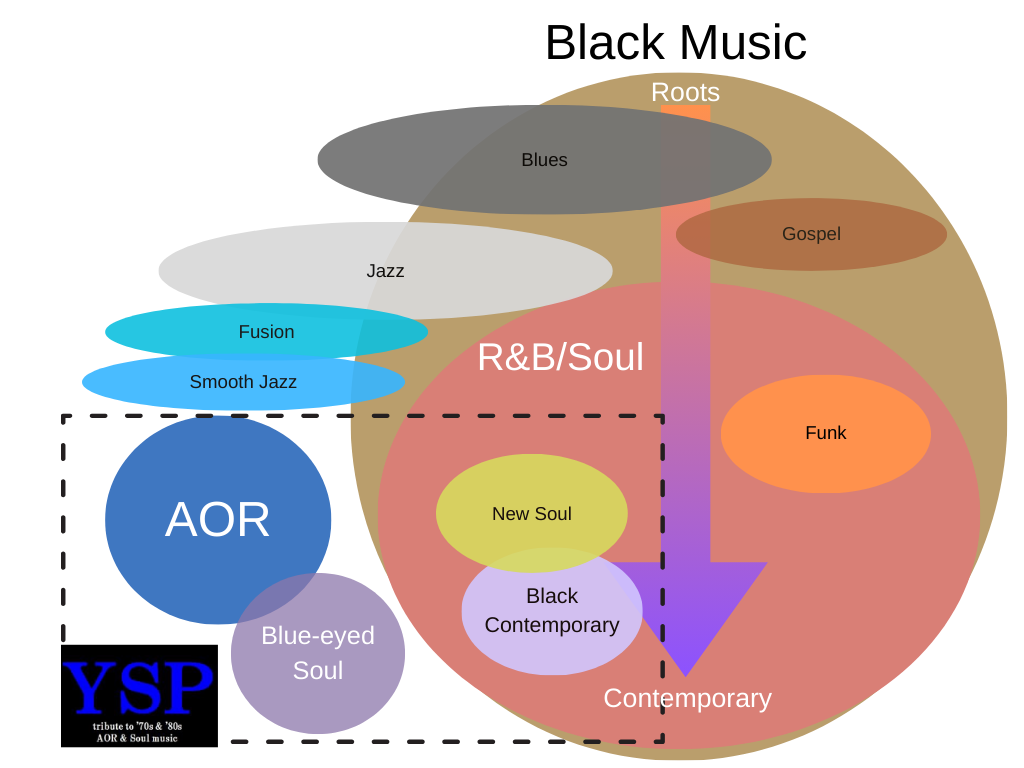
【YSPが演奏している楽曲の方向性】
大まかにいうと、上の図の破線で囲まれた部分に該当する楽曲のカバーを演奏しています。
ここでも、更に細かい用語(ジャンル)が出てきています。
◆ニューソウル
実は曖昧なワードで、もしかしたら日本独特の表現かもしれません。
1970年代前半から台頭したブラックミュージックで、従来よりは、メッセージ性の強い楽曲や、ベーシックなR&B/ソウルよりも広い音楽性を取り入れており、長尺な楽曲も増えています。
代表格としては、Donny Hathaway、Stevie Wonder、Curtis Mayfield、Marvin Gayeあたりかと思います。
YSPのレパから・・
◆ブラックコンテンポラリー
ニューソウル隆盛のあと、1980年代に入ると、ブラックミュージックの中でも、シンセサイザーやリズムマシン(所謂「打ち込み」ですね)の導入等、より洗練・デジタル化されたサウンドの楽曲が増え始め、これが、当時のメインストリームになっていきます。
代表的なところでは、Luther Vandross、Al Jarreau、Lionel Richieといったところでしょうか。
余談になりますが、1970~80年代のブラックミュージックは、アーティストをカテゴリーの枠に当てはめることは難しく、例えば、Marvin Gayeは、キャリアの初期は正にモータウンで、その後、ニューソウル的なポジションになり、晩年は、ブラックコンテンポラリーの作風となっています。
また、Stevie Wonderも、1985年のアルバム「In Square Circle」あたりは、「まさにブラコン」というサウンドです。
従い、音楽性で捉えるよりは、時間軸で捉えた方がよい呼称だと思われます。
曲調的に、AORとの相性もよく、YSPでは、1980年代の全盛期のブラックミュージック全体(例えばMichael JacksonやPrince等も含め)から選曲しています。
◆ブルーアイドソウル
文字通り、ブラックミュージックから影響された青い目(白人)のミュージシャンが演奏するソウルミュージックです。
代表格としては、Dary Hall & John Oates、The Average White Band あたりでしょうか。
こちらも、AORとの相性は抜群です。
Daryl Hall & John Oatesは、YSPでも取り上げています。
大体、イメージして頂けたでしょうか。
1970年代~80年代のAORや、ブラックミュージック(R&B/ソウル)の名曲を、これからもお届けしています。
この記事、気に入って頂けましたら、お友達に紹介してみて下さい。
よろしくお願いします!